研究紹介
- HOME
- 研究紹介

齋藤先生の研究紹介
私の研究の大きなテーマは人工子宮・人工胎盤システム研究になります。
日本の周産期医療の成績は世界の中でもトップクラスですが、早産率は5~6%程度で高止まりしていると言われています。また、高齢出産化に伴いこの傾向は今後も続くと考えられており、早産は大きな課題として横たわっています。
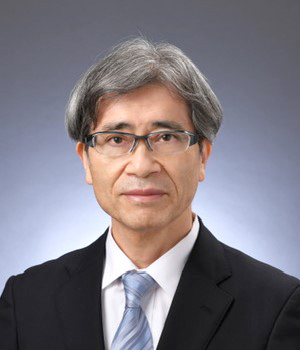
木村先生の研究紹介
赤ちゃんが満期より早く生まれる早産(妊娠22 週から36 週までの分娩)が世界的に増加しています。少子高齢社会の周産期医療において、早産児を救うことは重要な課題の一つです。また、早産児が新生児集中治療室(NICU)に入院すると、退院までに、早産児一人に対し多大な医療費が発生し、病院や家族に負担がかかります。ところが驚くべきことに、切迫早産の確実な管理法や治療法は未だ確立されておらず、世界各国でも統一されていないのが現状です。

笠原先生の研究紹介
赤ちゃんがお母さんのお腹の中で過ごす時間は、ヒトの体の基礎が作られる大切な時期です。この大切な時期にお母さんを通してお腹の中の赤ちゃんに伝わる様々な出来事は、赤ちゃんの将来の健康や病気のなりやすさに影響することがあります。このような考え方を「DOHaD」と言います。DOHaDとは「Developmental Origin of Health and Disease」の略称で、胎芽期・胎児期・生後早期における環境要因が将来の健康や疾患発症リスクに影響するという概念のことです。